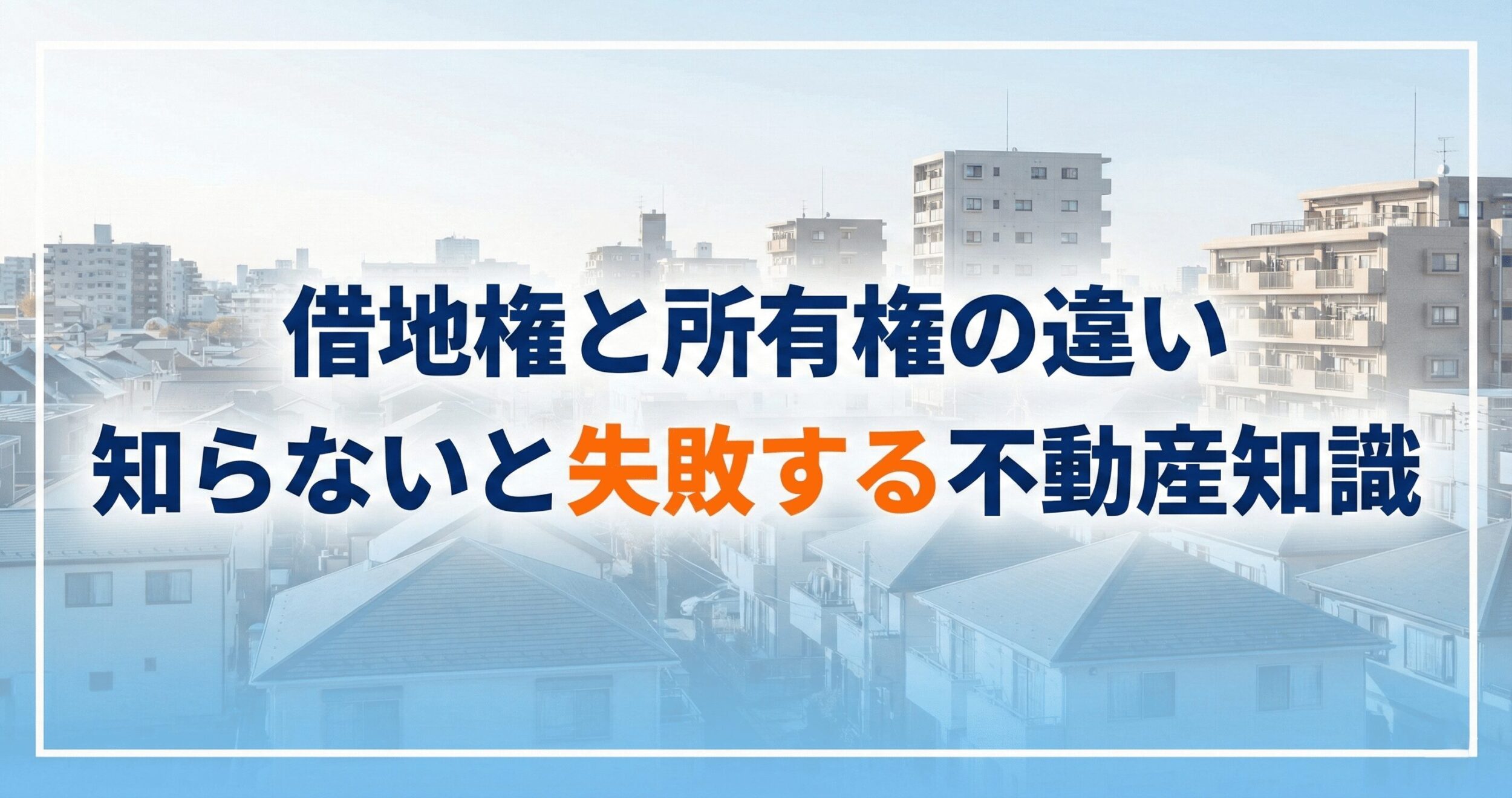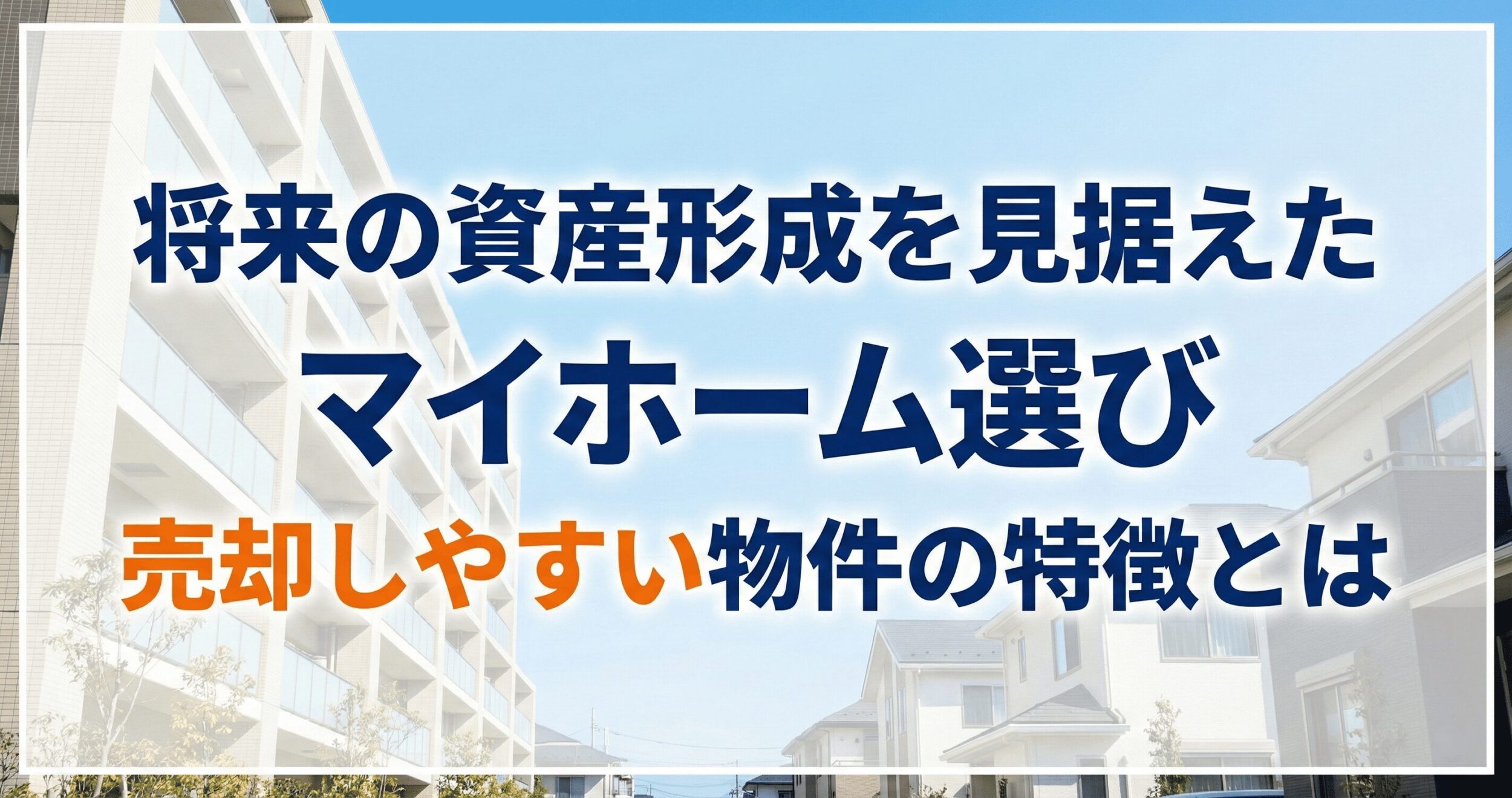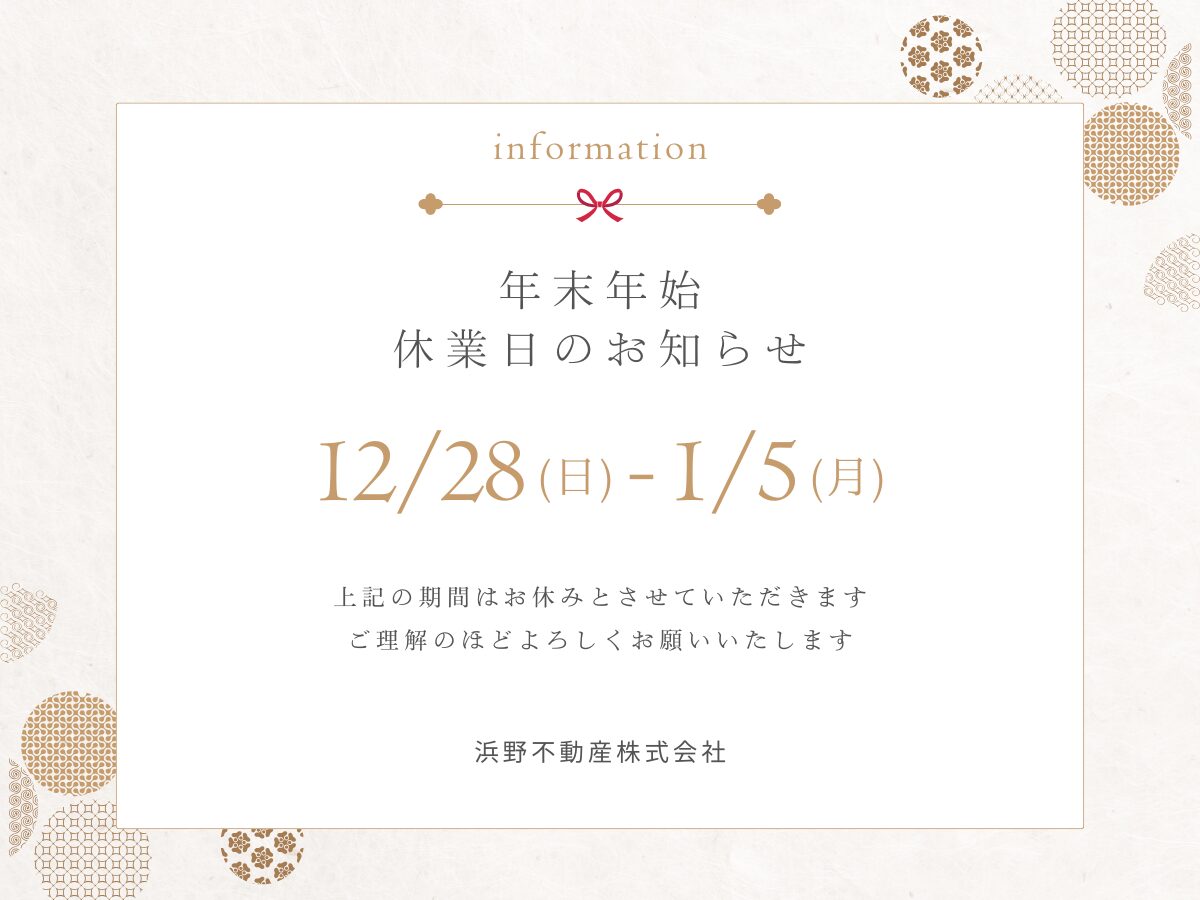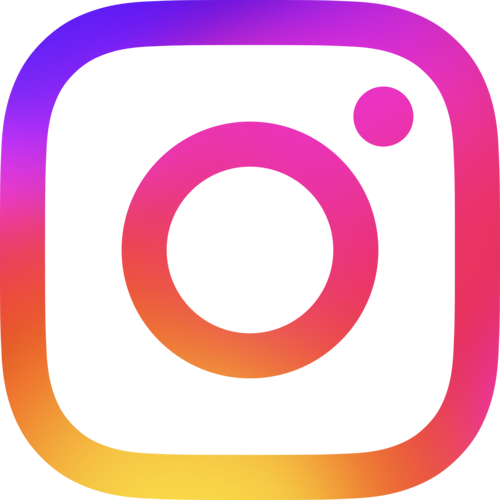2025.04.29
農地転用とは?空き家の敷地が農地だったときはどうする?

「農地転用って何だろう?」「畑や田んぼを家や駐車場に変えることはできるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
実は、農地は特別な土地なので、自由に使い方を変えることはできません。
たとえば、昔からある家のまわりの土地が「田」や「畑」のままになっていることがあります。このままだと、新しく家を建てたり、売ったりすることがむずかしいため、土地の使い方を変える手続きが必要です。
この手続きのことを「農地転用」といいます。
この記事では、「農地転用とは何か」「どうやって手続きするのか」「どんなときに必要なのか」などをわかりやすく説明します。
農地転用とは?
農地転用とは、田んぼや畑などの農地を、住宅・駐車場・お店など農業以外の目的に使えるようにする手続きのことです。
農地は、「農地法」という法律で守られていて、農業のために使うことが決められています。
そのため、自分の土地であっても、勝手に使い道を変えることはできません。
たとえば、畑を駐車場にしたいと思っても、そのままでは工事できません。
まずは、役所に申し込みをして、使い方を変えてもよいかの許可をもらう必要があります。
農地転用をすると、土地の使い方を正式に変えることができるようになります。
では、どんなときに農地転用が必要になるのでしょうか。
空き家の敷地が農地だったときは?
古い家が建っている土地でも、登記の内容(地目)が「田」や「畑」になっていることがあります。
このままでは、家の建て替えや売却がむずかしくなってしまいます。
このような場合は、まず「農地転用」の手続きをして、土地を「宅地(家を建てるための土地)」に変える必要があります。
農地転用は、農地法第4条や第5条というルールにしたがって進めます。
また、空き家を直して活用したいとき、その家のまわりの農地を駐車場や家庭菜園にしたい場合も、農地転用が必要になります。
さらに、空き家を解体して、農地の場所に新しく家を建てたいときも、事前に手続きが必要です。
このように、空き家と農地転用は、いっしょに考えられることが多くなっています。
農地転用の手続きはどうするの?
農地転用の手続きには、「許可」と「届出」の2つの方法があります。
農地が市街化調整区域など、建物を建てにくい場所にある場合は、農業委員会や都道府県から「許可」をもらわなければなりません。
いっぽうで、建物を建てやすい区域にある農地なら、「届出」だけで手続きが終わる場合もあります。
どちらの手続きになるかは、土地がどこにあるかによって決まります。
役所や農業委員会に相談すれば、自分の土地にどの手続きが必要か教えてもらえます。
申請には、書類の準備や現地の確認が必要なので、時間に余裕を持って進めることが大切です。
農地転用の注意点とは?
農地転用をするときは、いくつかの注意点もあります。
まず、許可を受けずに勝手に工事を始めると、法律違反になってしまいます。
場合によっては、元の状態に戻すよう命令されることもあります。
また、農地転用をすると、土地の税金が高くなることもあります。
農地のままなら税金は安いのですが、宅地に変えると評価額が上がり、固定資産税が高くなることがあります。
さらに、手続きには時間がかかるため、工事や売却を計画している場合は、早めに準備しておくことが大切です。
農地転用のメリットとは?
農地転用をすることで、土地の使い方の幅が広がります。
たとえば、畑だった土地に家を建てたり、駐車場にしたり、お店を開いたりすることができるようになります。
また、土地を売りたいときも、転用して宅地にしておけば、買ってくれる人が見つかりやすくなる場合もあります。
さらに、農地のままでは使い道が限られてしまいますが、転用すれば新しい活用方法が見つかるかもしれません。
まとめ
農地転用とは、田んぼや畑を住宅や駐車場などに使えるようにするための手続きだということをお伝えしました。
空き家の敷地が農地の場合や、農地の活用を考えているときには、必ず事前に手続きを行う必要があります。
土地を上手に活用するためにも、農地転用について正しく理解し、早めの準備を心がけましょう。